生態系
生態系グループでは、放射生態学に関わる調査を行っています。
【放射生態学】とは、環境中の放射性物質の挙動や放射性物質によるヒトや環境への影響について明らかにする学問で、原子核物理学、化学、生物学、毒物学、生理学、生態学、モデリング、リスク分析など、複数の学問領域にわたる総合科学です。東京電力福島第一原子力発電所の事故で、放射性セシウムをはじめとする大量の放射性物質が放出されました。そこで、環境汚染源となる放射性物質が、大気、土壌、湖沼、河川、農地、森林、動植物のどこに存在し、将来的にどのように変化するのか調査を行っています。さらに、動植物が環境中で受ける放射線量、健康への影響やリスクについて調査を行っています。
 |
 |
 |
活動記
  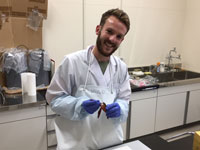 |
2017年6月20日~8月21日 | |
| 福島大学と連携しているイギリスのポーツマス大学の博士課程学生、ニール・フラーさんがこの夏、福島に滞在し、環境放射能研究所(IER)で調査を行ないました(指導教員:ポーツマス大学ジム・スミス教授、IER和田敏裕准教授)。この調査は、日本学術振興会(JSPS)外国人特別研究員サマー・プログラムの助成を受けたもので、低線量の放射線が甲殻類に及ぼす影響等を明らかにすることを目的としています。ニールさんは、帰還困難区域などで和田准教授らが採集したモクズガニ等の形態分析や放射性セシウムの分析を行いました。 [写真上:県水産試験場での勉強会に参加するニール・フラーさん(右)] [写真中:ため池で調査を行うニール・フラーさん] [写真下:サンプルを測定するニール・フラーさん] |
 |
2017年6月20日~8月23日 | |
| 福島大学の協定校であるコロラド州立大学(CSU)の修士学生、ダニエル・ワークマンさんがこの夏、福島に滞在し、環境放射能研究所(IER)で修士論文研究のための調査を行ないました(指導教員:CSUトム・ジョンソン教授、IERヴァシル・ヨシェンコ特任教授)。この調査は、日本学術振興会(JSPS)外国人特別研究員サマー・プログラムの助成を受けたもので、森林の下層植生(下草)における放射性セシウムの土壌-植物間移行係数(土壌から植物に移行する割合)が種や個体によって異なる要因を明らかにすることを目的としています。ダニエルさんは、ヨシェンコ特任教授とともに環境放射能研究所が福島県内に借りている観測林で土壌および数種類の植物のサンプリングを行なったほか、土壌の塊から植物の根だけを取り出す方法の開発、土壌中の植物の根の形態解析、土壌中の放射性セシウムの化学的形態分析などを行ないました。 [写真:帰還困難区域でサンプル採取を行うダニエル・ワークマンさん] |
 |
2016年9月21~29日 | |
| 和田敏裕准教授率いるIER研究者チームにノルウェー生命科学大学(NMBU)からの科学者10人が加わり、福島県内の様々な河川や湖沼で、魚類や水、堆積物等のサンプリングを実施しました。今回の調査データは、水圏生態系における放射性セ
シウムの挙動に関する共同研究として今後研究を進めていきます。 [写真:阿武隈川で堆積物を確認するDr. Hans-Christian Teien (NMBU)] |